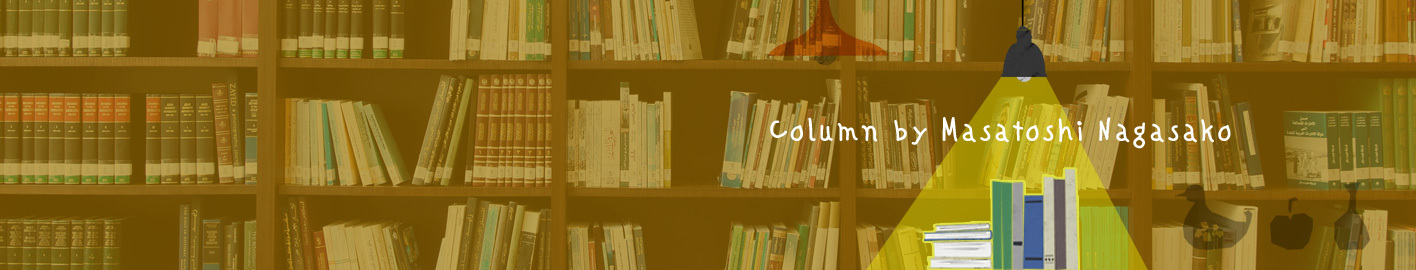おすすめの本RECOMMEND
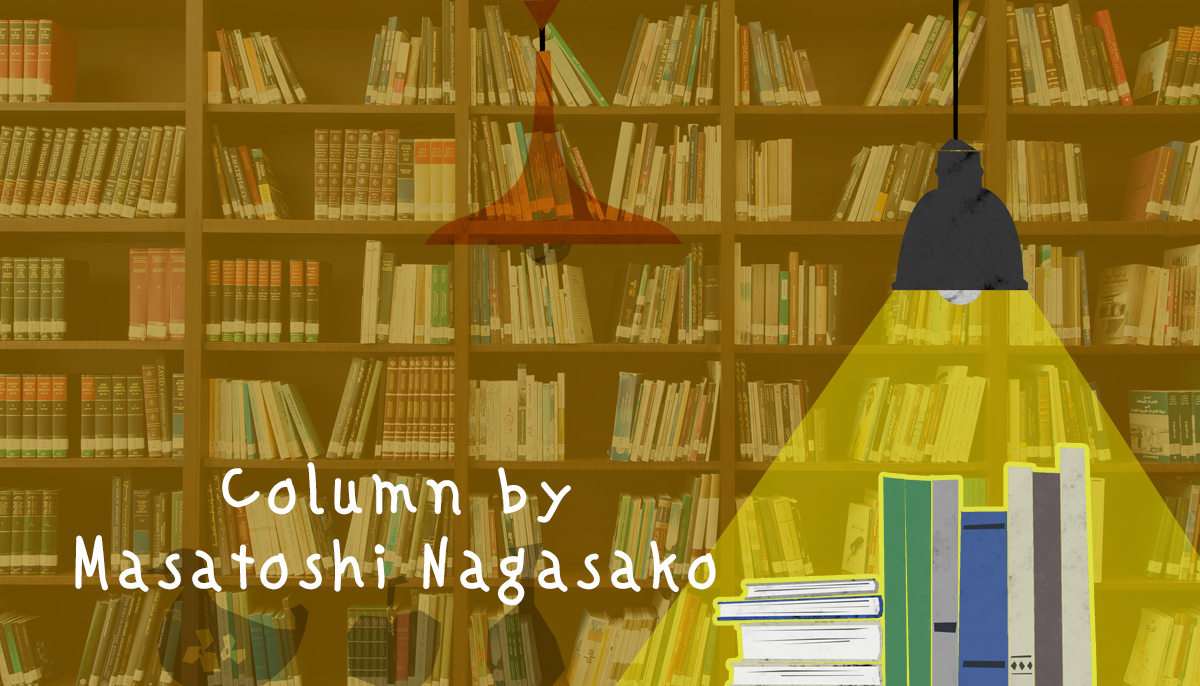
本さえあれば、日日平安
長迫正敏がおすすめする本です。
本さえあれば、穏やかな日日。ほっこりコラム連載中です。本好きのほんわかブログ・「本さえあれば、日日平安」
本好きの、本好きによる、本好きのための“ほんわか”。一日を穏やかに過ごす長迫氏のおすすめ本はこれ!
2025/08/16 更新
本さえあれば、日日平安
長迫正敏がおすすめする本です。
その他
建築知識 2025年8月号
著者:建築知識・編集部
出版社:エクスナレッジ

クラフト・エヴィング商會・吉田篤弘さんのエッセイ『金曜日の本』(中公文庫)を読んだ。1962年生まれの著者が、子ども時代の想い出と忘れがたい本について綴られた随想集である。
なかでもお父さんについて書かれたエピソードが印象的だったので、その個所を引用させて頂く。
とにかく父はなんでもよく知っていた。わからないことがあると、まず父に訊けばたいていのことは答えてくれた。
これには種明かしがある。
父の一家は戦時中、千葉の市川に疎開し、小さな古本屋に間借りをしていた。昼は古本屋の主人がいて店を開いているが、夜になると店を閉めて自宅に帰ってしまう。「読み放題だった」と父は云っていた。「店中の本をすべて読んだな」
父はそのとき十二歳だった。読んだものが血肉になっていた。父の体の中には、古本屋一軒分の知識と物語が蓄えられていた。
12歳にして古本屋一軒分の知識と物語が蓄えられていた、なんて凄すぎる。
やはり本は読んでおくものである。特に若い時には。
そう言えば一生のうちでどのくらい本が読めるものだろうか?
計算するとなると、まずは「何歳から何歳までとするか問題」がでてくる。もちろん字が読める年齢になってからということだが、親から与えられた本、宿題なので仕方なく読んだ…ではなくて自分の意志で選んで読み始めた時からとしたい。
ただ、それにしても個人差が大きい。小学生からの人もいるだろうし、中学、高校、なかには社会人になってから読書にめざめたという方もいる。またいつまで読めるかにしても幅がある。80歳過ぎても文庫本(主に時代小説)を読まれている現役バリバリの方もいらっしゃる一方で、老眼が始まり最近は全く本を読んでないと言われる50代の方も。
それに『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅香帆/集英社)ではないが、退職してから再度読み始めたが、働いていた間は読書「空白の30年」があった人もいるかも知れない。
その様に色んなパターンが考えられるが、便宜上10歳から80歳までの70年間を読書年齢と定め、単純に1年365日(12か月/52週)として計算する。
最低ラインで例えるなら、該当の70年間、年に1冊本を読んだ人の生涯読了冊数は70冊となる。
同様に計算していくと年2冊(半年に1冊)の人は140冊、年4冊(春夏秋冬、季節ごとに1冊)で280冊、月に1冊では840冊、月に2冊だと1,680冊、週に1冊だと3,640冊、3日で1冊なら8,517冊、2日に1冊で12,775冊。
そして70年間に渡り毎日1冊ずつ読めば25,550冊となる。
毎日2~3冊は読んでいるという特殊な人を除くと、年に1冊読んでいるという70冊から、毎日1冊読了しないと気が済まないという人の25,550冊までの間というかなり幅のある範囲となる。なのでより絞り込んで考えると月1冊の840冊から週に1冊の3,640冊の中間あたりで、2,500冊前後が生涯読了冊数の平均ではなかろうか。
「いやいやコミックスを含めていいなら一生涯ではなくても、もうそのぐらいは読んだし、家にもあるよ!」と言われる読書好きの人もいるだろう。あくまでも計算上なのでお許し願いたい。
以上のようなコラムの「まくら」になりそうなエピソードを休みの時に書いてはパソコンに保存しておき、紹介したい本に出会ったとき、「これいけるんじゃねぇ」と引っ張りだしては冒頭にもってくることにしている。
そこで今回のエピソードからは雑誌をご紹介。『建築知識 2025年8月号』、特集は「本と生きる空間」
表紙のイラストがとても良い。そそられる。もちろん中身は、もっとそそられる。
「住宅からカフェ、ホテル、図書館まで、読書が楽しくなる空間を大特集!設計者はもちろん、読書好きの方、ブックカフェや書店を経営したい方も必見です!」
1章「大量の本を保管する」から始まり、2章「狭い空間を最大限活用する」、3章「没頭できる空間を演出する」と続く。
「賃貸ワンルームに1,000冊の本を収納する」、「廊下を家族のライブラリーに」、「円形の本棚に家族の本を集約」など一般の住宅で活用できるアイデアが満載。
また「視線や音をカットして読書に没頭」できるカフェ、「本棚とベッドを一体化する」カプセルホテル、「本を媒介に会話がはずむ」本に囲まれた美容室など、読書好きならば行ってみたいと感じる店のレイアウトは興味深い。
他にも「蔵書を地域の子どもにシェアする」ことを考えた住宅、「床と本棚の高さを変えて多様な席をつくる」誰でも利用できる社内ライブラリー、さらに「幅広い世代に刺さる売場をつくる」地域に愛される駅ナカ書店である佐賀県佐賀市の「佐賀之書店」の店内配置図は、書店員として見逃せない。
パラパラと頁をめくるだけでワクワクしてくる。全体を表したイラスト、寸法が記載された詳細な図面、収容可能な蔵書冊数まで明記されている。これはもう完全保存版である。
ちなみに今回のコラムに関しては、完全書き下ろし版だったりする。